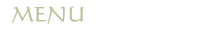NEW ENTRY
[PR]
36thday
だから大したことない、簡単と思っていたのに。
体ってこんなに重いものだったの?
意識するだけで跳べたのに、今は翼の力を借りて飛べるだけ。
剣が重い。
マナは簡単に振るっていたのに。
それでもやらないといけない。
宝玉を手に入れないといけないから。
まだ文字もうまく書けない。
(マナを見ていたから文字自体はわかっているけど、ペンの書き心地に慣れないし、紙を燃やしてしまいそうになる)
だけどマナは時々この島のことを書き残していたから、私も書き残していかなきゃ。
この島に来て35日目の探索日に・・・・私は生まれた。
◆ ◆ ◆ ◆
「華煉を見ておるのかのぉ?ふむ、あれも慣れぬ体にちょっと疲れておるようじゃな。」
後ろから声をかけられたが、口調で相手がすぐにわかる。
「清蘭殿か。よく来てくれたな。聞きたいことがたくさんある。」
華煉が生まれた日に立ち会った清蘭は外の様子を見れるようにしてくれた。
俺は火喰い鳥のナイフの中に魂を封じ込められているけど、華煉のそばに俺が立っているかのように周りが見れるように術をかけてくれた。
それに軽く戦闘の指南が出来るようにもしてくれた。
今の俺は近くにいる人になら声をかけることが出来る。叫んで声が届く範囲の人になら。
そして、俺は見た。
単純に俺の体という器に華煉の魂が入っただけだと聞かされていた。
だから、俺の体に異変はないと思っていた。
だが、華煉と言う魂を収容して・・・俺の体は髪の色、肌の色だけをそのままにして大きな変化を遂げていた。
丸みを帯びた体、長い髪
翼は俺よりも短くなった代わりによりあざやかに輝き、そして華煉との契約の印である胸の刺青はなくなり、俺の生まれ持った気質や守護者を現す額の刺青も消え、
ただ、訓練して体に叩きこんだ剣の力と祈りの力を示す両腕の刺青はそのままにして・・・女性化していた。
あの大火が鎮火したあとも華煉が触れる物はすべて発熱する状態だった。
俺の声を外に届くようにしてくれたから、みんなに頼んで俺の荷物袋を漁ってもらった。
少し前から華煉が織っていた布がいつの間にかそこに入っていて、華煉が着る服に困ることはなかった。
(服はハーカが手渡して着付けを手伝ってくれた。焔に強いハーカがいなかったらきつかっただろう)
今俺がいるのは火喰い鳥のナイフの紅瑪瑙石からつながる空間。
華煉は力を失ったと聞かれてたのに、なぜかこの空間だけはがっちりと固定され崩れることがない。
というよりも華煉の残り少ない全精霊力をここに常に流し込んでいるから、他には少しも使えないので力がないも同然となっているということだ。
ここを訪れるのは精霊のみ。それも華煉の力を阻害しない程度に華煉に近しいものだけだと言う。
清蘭が立ち去ってから、俺はずっとずっと外を見ることしか出来なかった。
「あれ、俺の体だよな。なんであんなふうに女性化したんだ?俺の形に戻ったりするのか?戻らないなら俺はもういいのに。華煉が無理に守護者と戦わなくても・・」
「ふむ・・・・一度は中途半端に燃やしたところで再生したからのう。変に華煉に意識が入って女性化したのじゃろう。あれはもう堕精化しかけておったから。」
「何?ダセイ?なんだそれ?」
聞いた事のない言葉を聞かされて、マナは首をかしげた。
「精霊が、精霊力を失い、ただの人に成り果てることを堕精化という。お主、御伽噺は知っておるか?火喰い鳥の里の始祖の話じゃよ。」
「あぁ、聞いたことはある。火の精霊が女性に恋をして・・・というあれだろう?肉体を持たない精霊が人との間に子どもをもうけるなんてありえないから、単なる御伽噺だと思っていたが違うのか?」
「違う。火の精霊はごくまれにその精霊力をすべて失い、精神体としての力を維持できず、受肉化することがある。当然、精神体としての力は振るうことが出来なくなり、肉体に宿る力のみを使うことが出来るようになる。もっともその肉体にも火の息吹が宿り続けるので、発火することができるヒト・・・・つまり火喰い鳥の民になる。おぬしら火喰い鳥の民の始祖は霊力を失った精霊じゃよ。」
「・・・ちょ・・・すまん・・・俺たち以外にも火の力を持ってる奴っているよな?俺たちだけそんな特殊な民なのか?信じられん」
「本来、火の力というのは生命と合わぬものよ。
生命(有機体)というのは、水を吸収し、大地(に含まれる無機物やミネラル)を吸収し、他の生命の体(有機物)を吸収し、生きるもの。
火は水を蒸発させ、大地を不活性にし、他の生命すら空へと変えてしまう、純粋な熱エネルギーの塊。生命の器にはそぐわぬものよ。
それを備える生命は何かしらの力で火を召喚出来るものか、特殊な力を持っている者に限られるのは当たり前じゃ。」
当たり前といわれても、すぐには信じられなかった。
生まれたときから火を取り出すのは、周りのみんなが出来たことで、特殊なことだなんて思ったことはなかった。
確かに里を出てから、誰もが火を使えるわけではないと言うことを知ったし里の結界のおかげで発した火が燃え広がらないように制御されていたのだと言うことも知った。
自分の不注意で山火事一つ起こしかけてしまったことだってある(華煉がすぐに消したが・・・)。
だから、火を扱えるのが特異なんだと言うことは気づいていたが、自分が特殊な能力者だなんて思ったことは一度もない。
舞華みたいに超長生きしている方がよっぽど特殊だと・・・そう思っていた。
何やら考え込んでしまったマナの様子を見て、清蘭はため息をついた。
「ふぅむ。困ったのぉ。この程度の情報でこんなに混乱されては話がまったく先に進まんではないか。
すまんが、儂が話すから、信じられなくてもいいからとにかく黙って聞いておいてくれんかのぉ」
マナは顔をあげて清蘭の方を見返した。
確かに信じられないが、信じられないといえば、自分の魂がこんな風に隔離されて、肉体が女性化したことだって信じられない。いちいち驚いていてはいけないのだろう。
マナは腹をくくって、頷いた。
◆ ◆ ◆ ◆
清蘭は語った。
最初の火喰い鳥の民は、ヒトを愛し、ヒトに憧れて、すべての力を失い惰性した火の精霊だった。
今思えば彼には火の力を注ぎ込んで即座に転生させておくべきだった。
だが、彼はヒトとの間に子をなすことを望んだ。ただのヒトの子宮は焔に耐えることが出来ない。
火の力を有した受精卵は母親のお腹の中で育っていく中で火の霊力に開眼し、母親の体ごと焼き尽くした。
何人かの母親が死んだあと(この時点で彼を殺しておくべきだった)、彼を哀れんだ火の精霊王が胎児の力を弱めた。
力の弱まった胎児は母親の胎内にいるうちから魔に取り込まれた。
今の火喰い鳥の民もそうだが、火の精霊の力をもったその胎児は魔の媒体として最適な器だったのだ。
胎児は生まれると同時に母親を焼き殺し、彼はそのまま魔に食い殺された。
それも単に食い殺されるだけでなく、実界に大きな災害を引き起こす大魔法の媒体とされ、魔法の完成と共に生贄として命を奪われ死を迎えた。
この世界は大きく乱れ、精霊たちは多くの介入を行わざるを得なかった。
このような危険な民を放置は出来ない。
だが、すでに何人かの胎児の魂が・・・生まれる前に母親を焼き殺した子らの魂が転生の輪の中に組み込まれていた。
そこで、何人かの強い力を持った精霊が自らの霊力を封印し、自ら堕精し、火喰い鳥の里を作った。
彼らの力は封印されただけなので、死を迎えると同時にその体を焼き尽くすことで、火の精霊として転生できる。
また、彼らの間に出来る子は強い火の力を有していたので、死した後に体を焼き尽くすだけで火の精霊として転生することができた。
強い火の力を持った胎児が安全に生まれるように卵で生まれる形態をとり、さらに里を火の精霊たちが守ることで孵化の瞬間も魔に取り込まれる事のない安全なシステムが生まれた。
おまけに守護精霊として強い力を持つ火霊までつけた。
転生の輪の中で彷徨っていた魂は、火喰い鳥の民として生まれ、そして死んだ後は強い火の力で燃やすことでその魂のほとんどが火の精霊へと転生した。
強い火の力で燃やし尽くすと同時に力の残滓を残さないために、守護精霊が火喰い鳥の民の魂を焔で送り、その体に残った力を吸い尽くす儀式まで作られた。それが今に至るまで続く昇華の儀式。
今では最初の意図は忘れられ、守護精霊の力を増すための儀式と考えられているが、そうではない。
すべてのシステムは堕精した火の精霊の残滓を火の精霊に返すことを目的として作られていた。
もちろん火喰い鳥の民とヒトの間に出来た子どもの魂なので、どれほど強い火の器に入れても、火の精霊に転生できずにもう一度火喰い鳥の民へと転生する魂もなかにはあった。
とはいえ、数世代も繰り返せば、すべての火喰い鳥の民は火の精霊に戻り、この危険な民はなくなるはずだった。
だが、なぜか(やはり半人の魂が混ざったためか?)新たに堕精する者も現れ、火喰い鳥の民は一向にその数を減らすことがなかった。
やがて、何度も転生を繰り返すのを見ていたある者が気づいた。
最初に魔の力をうけ、食い殺された子ども・・・イールの魂だけは、何度繰り返しても火の精霊へと帰らないことに。
イールの魂を宿す火喰い鳥の民を守護する守護精霊は常に同じ魂を持ったもの。
最初に堕精した火喰い鳥の民・・・イールの父親の魂を持つものがずっとずっと守護精霊としてつき、何度も何度も同じタイミングで転生していることに。
そして、イールを守護する守護精霊が高確率で堕精していることに。
イールを火の精霊に転生させなければこの連鎖は止まらない。
火の精霊は総力を上げてイールに火の息吹を吹き込んで、火の精霊に転生させた。
だが、対となる守護精霊の魂が今度は火喰い鳥の民として転生してしまった。
「どれだけやっても、必ずどちらかの魂が火喰い鳥の民に、残る魂は火の精霊に転生した・・・・そしてその火喰い鳥の民は常に対となる魂を有する精霊を守護精霊に選んだ。
この二つの魂の呪いは今も解けていない。長い年月を重ねる中、その特殊な二つの魂のどちらがイールの魂で、どちらが父親である燦伽(さんか)の魂なのかわからなくなってしまった。だが、今生におけるその二つの魂が誰であるかはもうわかっている。お主と華煉じゃよ。」
PR
- トラックバックURLはこちら